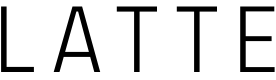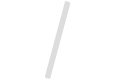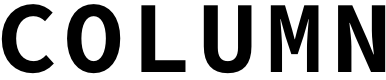イギリス生まれの「ペンギンブックス」コレクタブルなヴィンテージ本&雑貨
イギリスをはじめ、英語圏ではよく知られているペーパーバック「ペンギンブックス」シリーズ。なかでも1930年代から60年代までに出版されていたツートーンカラーの本は、コレクタブルな人気アイテム。そのエピソードと、本をモチーフにした雑貨の紹介。
オレンジやグリーン、またはブルーやピンクにホワイトを組み合わせたツートーンカラー。
そこにペンギンをあしらったエコバッグやマグカップを目にしたことはありませんか?
このペンギンは、英語圏では有名な「Penguin Books(ペンギンブックス)」のロゴマークです。

Penguin Books 公式サイト https://www.penguin.co.uk/ より引用
1935年にイギリスで創業されたペンギンブックス社(現在はランダムハウス社と合併して「ペンギン・ランダムハウス社」に社名を変更しています)は、それまでに出回っていた粗悪な製本と、垢抜けないデザインのペーパーバックを一新させることに成功しました。
日本の文庫本に相当する欧米のペーパーバックは、多くの出版社から発行されていますが、その草分け的存在と言えるのが「ペンギンブックス」シリーズ。
古典や名作から最新作に至るまで、タイトルが豊富なだけでなく、その装丁が美しいことでも知られています。

斬新で可愛らしいデザインが多いことから、読みものとしてだけではなく、コレクタブルなアイテムとしても注目されています。
特に人気があるのは、初期に販売されていたツートーンカラーのペーパーバック。
イギリスでは、アンティークショップの定番で、インテリア雑誌には空間を彩るデコレーションとしてもよく登場します。
ハードカバーほどではないにせよ、庶民にとってはまだまだ高価であったペーパーバック。
それを手頃な価格で販売しようと努めた同社は、書店だけではなく、チェーンの大型量販店などでも書籍の販売を始めました。
1冊6ペンス。
価格をタバコ1箱と同じくらいに設定し、誰もが本を手に取ることができるようにしたのです。
そしてなによりも画期的だったのは、本を分類ごとに色分けして、見た目で本の内容を明らかにしたことでした。
このシンプルなデザインは、写真印刷の技術が発展する1960年代まで続きました。
- オレンジ フィクション
- グリーン 推理小説・ミステリー
- ピンク 旅行書
- ダークブルー 伝記
- レッド 演劇・戯曲・脚本
- パープル エッセイ・純文学
- グレー 国際情勢
- イエロー 雑記
現在このデザインの本は出版されていませんが、イギリスの保守系高級紙「タイムズ」の付録として復刻版が発行されたことで一時、話題となりました。

このツートーンカラーのペーパーバックは、見た目にも美しく機能的でもあるため、コレクターには非常に人気が高いといいます。
最初にご紹介したエコバッグやマグカップなどの雑貨は、このレトロなデザインを再現したものなのです。
よく見ると、真ん中の部分には、チャールズ・ディケンズ著「Great Expectations(大いなる遺産)」やジェイン・オースティン著「Pride and Prejudice(自負と偏見)」などの名作のタイトルが記されていることに気がつくでしょう。

鮮やかな色づかいで、見た目にも美しいペンギンブックスをかたどった雑貨は、日本国内でもオンラインショップなどで購入できるほか、イギリス土産としても人気があります。
ツートーンカラーのヴィンテージ本に興味をお持ちなら、古書専門店やアンティークショップをこまめにのぞいてみてください。
本好きにはたまらない、そして、文学好きな人への贈り物としても喜ばれそうな「ペンギンブックス」のペーパーバックと雑貨。
その歴史と配色の意味を知ることで、そのツートーンカラーのデザインがいっそう価値のあるものに見えてきたのではないでしょうか。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

旅行とマーケット・蚤の市めぐりが大好きな庶民派ロンドナー。
コレクションのヴィンテージ食器を眺めている時に幸せを感じます。
ロンドン発 -庶民的生活-
http://workingclass.blog109.fc2.com/
Travel.jp「たびねす」にてガイド記事執筆中
http://guide.travel.co.jp/navigtr/707/
|
|
|