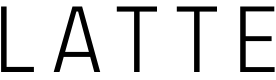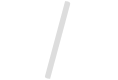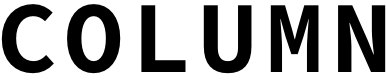脳はどうやって「雑音」と「音楽」を区別する?MIT研究チームがメカニズムを解明!
「音楽」が脳で処理されるメカニズムが徐々に明らかになりつつあります。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームによって発表された研究内容を紹介。
こんにちは。ピアニストの小川瞳です。
今回は「音楽と脳の関係」について、最近発表された研究内容を少しご紹介しましょう。

雑音ではなく、脳で意識的に理解する音に、「音楽」と「会話」があります。
では、音楽と会話は、どちらが先に誕生したのでしょうか?
諸説ありますが、最近では、「音楽が先に誕生し、会話は音楽が進化して生まれたものだ」という説が有力になってきています。
究極の話、音楽のほうが集団を結びつける力があるので、人間が協力しあって生きていくために必要なものだったと思われるのです。
会話は、そうやって生きてきた人間たちが、種として生き延びるために必要となり、言語というものが作り出されたのではないかと言われているのです。
人間の脳には、「聴覚野」と呼ばれる領域があります。
聴覚野とは、耳の神経からの信号を「音」として受け取る場所で、物音だろうが、話し声だろうが、音楽だろうが、同じ「音」として知覚するのです。
ですが、脳には雑音とは異なる「音楽」を「音楽」として認知する仕組みもあるということが、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームによって解明されました。
この研究チームが行った研究は、脳内の血液の動きを視覚化する装置を用いて、脳の活動を測定したのです。
すると、聴覚野の中には2つの領域があって、雑音を処理する領域と、音楽に特化した領域が存在することが明らかになったということです。

歌詞のある歌が聞こえてきたときは?
話し声を聴くと、雑音を処理する領域が反応を示し、音楽に特化した領域は無反応。
音楽を聴くと、その逆の現象が起こります。
ただ、驚くことに、歌詞のある歌が聞こえたときには、両方の領域が重なり合うように反応を見せたそうなのです。
音楽を聴くことは、脳トレにもつながる
音というのは、空気の振動によって脳に伝えられるわけですが、雑音ではなく音楽という形を成したとき、その音から人間はさまざまなものを感じ取ります。
あるときは感情が揺さぶられたり、あるときは何かの情景を思い起こしたり、リラックスや快眠に役立ったりします。

それは、脳に秘められた高度な処理能力によるものなので、音楽を聴くことによってそういった楽しみを感じることは、脳トレにも繋がると言われています。
ですから、時間があれば、音楽をただ聴き流すのではなく、音楽に浸って、自分の感情や思考と向き合う機会を作ってみてください。
普段からそういった時間を作っていると、自然にいきいきとした自分になれて、アンチエイジングにも役立つことでしょう。
元をただせば、「音楽」は単なる空気の振動。
それを脳が雑音などとは区別し、音楽として認知するとは、なんと高度な処理がされているのでしょうか。
音楽が会話よりも早く誕生したという説は、それほど音楽が人間にとって欠かせないものであるということを改めて示しているように思われます。
音楽が脳で処理されるメカニズムは、徐々に明らかになりつつあります。
また、新たな研究結果が発表され、不思議が解明される日がくるのが楽しみですね。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

ピアニストとして東京や茨城を中心に、ソロの演奏会やオーケストラとの共演など、数多くの演奏活動を行っております。
音楽心理士の資格も持ち、トークコンサートやコンクールの審査員もつとめております。
また長年に渡り執筆活動も並行して行っており、小説を3作品出版しております。
こちらのサイトでは、幼少時よりピアノを学び続け、クラシック音楽の世界に身を置く私ならではのコラムを執筆できたら、と思います。
よろしくお願い致します。
小川瞳 公式ホームページ https://ogawahitomi.amebaownd.com/
小川瞳作曲 笑顔のBGM
https://youtu.be/Qrt-stZPTb8
|
|
|