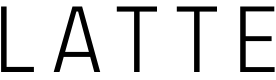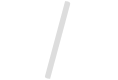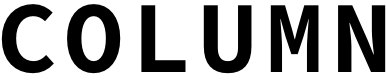身の毛もよだつ【恐怖の怪談話】2分~5分で読める怖い話短編集
短編の怪談話は好きですか。 何気ない日常に潜んでいる、奇妙な現象や不思議な話をオカルト研究家が選びました。4つの話の怪異に、あなたはどこまで耐えられるでしょうか。
こんにちは。オカルト研究家の洋子です。
今日は、私の知る短編の怪談話から、特に印象的なものを選んでみました。
オカルト研究家として、日々奇妙な現象や未解決の謎を追う私が、あなたを不思議に満ちた怪談話の世界へお連れします。
Aさんの息子のJ君は当時、小学3年生。J君はその日、1カ月以上前から楽しみにしていた遠足に出かけました。
「お母さん、お弁当おいしかったよ。ごちそうさま!行ってきまーす!!」
遠足から帰ったJ君は、台所の流し台に弁当箱と水筒を置いて、元気よく遊びに出ていきました。Aさんが弁当箱を持ち上げて振ると、カラカラとよい音がし、Aさんは「きれいに食べてくれたのね」と嬉しくなりました。
しかし、なぜか水筒はズッシリと重く、Aさんは首を傾げました。
台所の流しに水筒を傾けると、水でもジュースでもない、ザラザラとした“何か”が飛び出してきました。まるで、冷えて固まった血液のような、赤黒い色をしています。
驚いたAさんは、慌てて水筒を傾けるのをやめました。水筒の底を確認すると、目印にと貼ったはずの、J君お気に入りの昆虫ヒーローのキャラクターシールがありません。
タイミングよく帰ってきたJ君に、Aさんはたずねました。
「J君、この水筒ってJ君ので間違いないかな?」
J君は一瞬考えた後に、「あっ!」と思い出しました。
「Kちゃんと『水筒、同じだね』って話した。お弁当を食べた時に、間違えちゃったのかも」
KちゃんはJ君と同じクラスで、いつもうつむいてボソボソとしゃべる女の子でした。一方で、Kちゃんのお母さんはいつもきれいに化粧をしている、とても社交的な人でした。
「Kちゃんの水筒のジュースね、真っ赤で甘い、いい匂いがしたんだよ。『ちょっと飲ませて』って言ったんだけど『これはお薬だから、ダメ。全部ちゃんと飲まないと、おかあさんに怒られる』って、断られちゃったんだ」
「明日学校で返してくるね!」
無邪気に笑うJ君に、Aさんは何も言えず、水筒を手渡しました。次の日になり、学校から帰ってきたJ君に、Kちゃんへ水筒を返したかたずねると、「風邪で休みだった」と答えました。
その日の夕方、玄関のチャイムが鳴り、Kちゃんのお母さんがAさん宅を訪ねてきました。
「こんばんは。突然おじゃまして、すみません。うちの子が間違えて、J君の水筒を持って帰ってきてしまったようで、お届けに来ました」
いつも通り、きれいにお化粧したKちゃんのお母さん。Aさんは、水筒を持ってきてくれたお礼と、Kちゃんの体調はいかがですかとたずねました。
「お薬ちゃんと飲んだ?」
Kちゃんのお母さんにJ君がたずねると、それまで笑顔だったKちゃんのお母さんの表情が、強張ったような気がしたとAさんは言います。
「・・・ええ。たくさん飲んだからすぐに良くなるわ。心配してくれてありがとう」
Aさんの家には、J君が持ち帰ったKちゃんの水筒がありましたが、AさんはKちゃんのお母さんに返してはいけない様な気がしました。
チラチラと、何かを探るような視線を感じましたが、Kちゃんのお母さんもKちゃんの水筒については何もきかずに帰って行きました。
J君が返してもらった水筒の中身は、空っぽでした。しかし、Aさんは何となく気味の悪い感じがして、J君のお気に入りだったその水筒も、Kちゃんの水筒も、2つともこっそり捨ててしまいました。
Kちゃんのお母さんが、Aさんの家に水筒を返しに来てから一週間ほど経った頃。Kちゃんが病気で亡くなったと、J君のクラスで発表がありました。
Aさんは、今でも時々思うそうです。Kちゃんの水筒に入っていたのは、本当にジュースだったのだろうか? と。
「たぶん、私の聞き間違いなんです」
そう語るIさんは、あの雪山事件で唯一、生き残った人物だ。
Iさんたち、W大学スキーサークルのメンバー5人は、N県の山奥にやってきた。
本当はいけないと知りつつも、立ち入り禁止区域にこっそりと入り込み、誰の足跡もない新雪の上でスキーをするのが、W大学スキー部の伝統だった。
その日は、スキーを楽しむだけではなく、新入生の勧誘に向けたチラシを作るために、スキーサークルのメンバーの写真を撮るのが、Iさんの大切な仕事だった。
Iさんは、この日のために買った一眼のミラーレスカメラで、サークルメンバー4人の写真を次々と撮りためていった。
真っ青な空に太陽が輝く絶好のスキー日和に、天候が悪くなるなんて誰が想像しただろう。
突然空が真っ暗になり、ものすごい吹雪がおこったという。吹雪はどんどん激しくなり、視界が遮られたIさんは、前を滑っていたはずの4人とはぐれてしまった。
せめて吹雪が少しでもしのげる場所に行こうと、進むIさんの目の前に、いきなり山小屋が現れた。
助かった!と、 Iさんは何の疑いもなく山小屋に入ると、あたたかい毛布と暖炉、薪やマッチなど火を起こせるものがあった。
電気は通っておらず、照明はつかなかったが、SNSで見たスマートフォンのライトの上に、ペットボトルを置くと光が拡散されるという方法を試した所、部屋の中全体がぼんやりとだが見えるようになった。
壁にはいくつか写真が掛けられていて、白黒写真からセピア写真、そしてカラー写真と年代が様々で、この山小屋はどうやら長く使われてきた場所らしい。
スマートフォンの電波が入らないことは確認済みだったので、Iさんは何だか心細くなり今日カメラで撮った写真を見返すことにした。
外は変わらずものすごい吹雪で、隙間風によって室内のあらゆるものが、ガタガタと音を立てていた。
カメラにおさめられた写真は、N県の駅に着いた全体集合写真から始まり、お昼の温かくて美味しかった蕎麦や、帰りに行こうと約束していた温泉の前で撮った写真など、数時間前のことなのに、Iさんはかなり時間が経ったように思えた。
カチコチと、カメラの液晶画面の確認を進めていく。サークルのチラシ作りのために、個人写真も何枚か撮っていた。
普段は写真に写りたがらないA子が、照れくさそうにはにかんでいる。いい写真、これぞベスト写真だな! と思っていると、突然ザザーーーッと、カメラの液晶画面が乱れ、砂嵐が走った。
疑問に思いながらも、次の写真を見るとお調子者のSが、珍しく変顔をせずにさわやかな風貌で写っている。黙っていればイケてるのに、とほほ笑むとまた、液晶画面に砂嵐が走った。カメラの調子が悪いんだろうか。
次に出てきたのはY先輩。さすが去年のミスコン1位、女神のようなほほ笑みを浮かべている。拡大して壁に飾りたい美しさ! うっとりしていると、またまた奇妙な砂嵐が走った。
勘弁してくれよ、このカメラ高かったんだぞ。Iさんはそう思いながら、そういえば昔、テレビが故障した時に父親が叩いて直していたなと思いだし、カメラをコンコンと軽く叩いてみた。
最後はOちゃんだ。少しふくよかな彼女は、色白なこともありサークルメンバーから“お餅ちゃん”と呼ばれている。糸目になった満面の笑顔が、かわいらしい。
どれもいい写真だなと思っていると、ザザザザーーーーッと画面に強烈な砂嵐が起こり、プツンッと電源が落ちて真っ暗になった。次の瞬間、部屋の隅の方の暗闇から、ぼそりと声が聞こえたという。
「ベスト写真だね」
その次の瞬間、ガタガタと山小屋が強い吹雪にさらされて、大きな音を立てて揺れた。
Iさんは心臓がバクバクと鳴るのを感じながら、気のせいだ、きっとそうに違いないと思った。
しばらく緊張で体を強張らせていたそうだが、暖かい暖炉の火にあたり、毛布にくるまっていると、睡魔が襲ってきた。
Iさんは、「記憶を混同させているだけだと思う」というのだが・・・瞼を閉じかけながら見た壁に黒い額縁が4枚。Iさんがよい写真だと思った、4人のサークル仲間の個人写真が、山小屋の壁に並んでいるのを見たという。
次にIさんが目を開けたのは、病院のベッドの上だった。
Iさんが見つかったのは、山小屋ではなく大きな古い木に空いた空洞の中だった。ちょうど風よけになり、体温は急激に低下していたものの低体温症にならずにすんだのは奇跡的だった。
そして、Iさんが見つかった場所から、数メートル間隔で倒れているサークルメンバー4人が見つかった。
全員が右か左半身に獣に切り裂かれたような後があり、亡くなっていた。
今にして思うと、なぜあんな所に山小屋があったのか。
そもそも山小屋なんて本当にあったのだろうか。Iさんは記憶が曖昧だが暗闇から聞こえたあの声を思いだし、いまだに夜中に突然目が覚めるという。
また、Iさんが撮った4人の写真は、遺族から望まれて遺影となった。悲しくも、あの声が言っていたように、『ベスト写真』として4人の人生を締めくくる1枚となった。
ユウキは、道端で怪我をしているハムスターを見つけた。弱っているようだったので、ユウキは家に持ち帰って世話をすることにした。
ユウキの家は最近、不穏な雰囲気に包まれていた。両親は毎日のように激しい口論をし、家の中はいつも緊張感が漂っていた。しかし、ハムスターが来てから、家の中の重い空気が少しずつ和らいでいくのを、ユウキは感じた。
ある晩、ユウキは不思議な夢を見た。夢の中で、ハムスターが話しかけてきたのだ。
「ぼくを助けてくれてありがとう。お礼に、きみとお父さんお母さんの絆を取り戻す、お手伝いをさせてほしい」
夢の中でハムスターはユウキに、家族の絆を取り戻すために何をすべきか教えてくれた。
朝になり、目が覚めたユウキは夢の中で聞いた通りに行動し始めた。両親に対して、「ありがとう」と積極的に感謝の気持ちを表すようにし、「僕は寂しい。家族で過ごす時間を大切にしたい」と気持ちを伝えた。
最初は驚いていた両親も、徐々にユウキの提案に応じるようになり、家族の間に暖かい雰囲気が戻ってきた。
しかし、幸せな時間は長くは続かなかった。ハムスターが行方不明になったのだ。ユウキは必死に探し回ったが、どこにも見つからなかった。
その夜、ユウキはまた夢を見た。夢の中で、ハムスターがまた話しかけてきた。
「ぼくの役目は終わった。きみたち家族の絆はもう固く結ばれている。だから、安心してぼくを手放してほしい」
ユウキは、泣きながら目を覚ました。お母さんに夢のことを伝えると、あるサイトを見せながら「シロは神様のお使いだったのかもね」といった。
シロはハムスターの名前。毛並みが真っ白なのに、ジャンガリアンハムスターのように背中に黒い一本線が入っているのが特徴だった。
お母さんが見せてくれたのは、夢占いについて書かれたサイトだった。夢に現れる白いハムスターは『神様の使い』なんだそうだ。
ユウキは、涙を流しながらシロに感謝した。そして、家族の絆をこれからも大切にしていくことを心に誓った。
郊外のベッドタウンであるO市から、都心であるS区へ向かうその通勤電車は、毎朝大混雑だ。
乗客たちは疲れた顔で身を寄せ合い、なんとか自分のスペースを確保している。しかし、その中に一つだけ、いつも空いている席があった。
ある日、新しくこの路線を使い始めたサラリーマン・田中は、その空いている席を見つけてラッキーだと思い、座った。しかし、彼が席に座った途端、周りの乗客が一斉に彼を見つめ、怯えた表情を浮かべた。田中は理由が分からず、ただ不気味に感じていた。
翌日、田中はまたその席が空いてるのを見つけて、座った。すると、隣に座った老婦人が低い声で「あなた、その席に座らない方がよかったわよ」と言った。田中は驚いて理由を尋ねたが、老婦人は答えず、二度と田中と目を合わせなかった。
その次の日、連日の深夜残業でろくに眠れていなかった田中は、昨日の老婦人の言葉を思い出しながらも、ひどい眠気に勝てずに再びその席に座った。
今度は何かが違っていた。席に座ると、全身が急に寒くなり、息が上手くできなくなった。
恐怖に駆られた田中が慌てて飛び上がり、座っていた席を振り返ると、そこには全身血まみれのスーツ姿の男が座っていた。男は田中をじっと見つめ、まるで何かを訴えかけるように手を伸ばしてきた。田中は恐怖のあまり、逃げるようにして電車を降りた。
その日の夜に、田中は奇妙な夢を見た。夢の中で、田中はあの電車に乗り、あの空いている席の前に立っている。席に座った、あの全身血まみれの男と向き合い、何かを話そうとするのだが、声が出ない。真夜中にも関わらず飛び起きた田中は、水でもかぶったかのように全身汗だくだった。
次の日から、あの席に座ることはもちろんなく、乗る電車も変えたが、田中は変わらず毎晩同じ夢を見続けた。恐怖にかられた田中は、小さい頃からO市に住み、同じ路線を使っている先輩の高橋に相談することにした。
高橋は、「いつも空いている席が」と田中が話し出しただけで、怯えた表情をした。高橋がまだ高校生の頃に、その事件はおきたのだという。
男性Kさんは、O市よりもっとずっと郊外の、T市から毎朝通勤していた。T市の最寄り駅は電車の始発のため、必ず座ることができた。Kさんはいつも同じ時間の同じ車両の同じ席に座って出勤していたという。
その日もKさんは、いつもと同じ時間に、いつもと同じ車両のいつもと同じ席に座った。ただし、いつもと違うことがあった。Kさんはその日、電車の中で起こった殺人事件に巻き込まれて命を落としたのだ。
刃渡り30㎝の包丁によってめった刺しにされたKさんは、病院に運ばれる前に電車の中で息を引き取った。それからというもの、Kさんが座っていた席に座った人に、次々と不幸がおこるようになった。
席を封鎖してしまえばいいという声もあったが、できなかった。公共の場であることや、座った人におこる不幸というのが、電車に乗る人たちの間で都市伝説的になっていて、大っぴらに動くことがためらわれるものだったからだ。
犯人の供述によると、犯人の男とKさんに面識は全くなかったという。
「無差別だったんだって。やりきれないよな」
また、Kさんにとってその日は特別な日だった。勤めていた会社を辞めて、学生の頃からの夢だった、バックパッカーでの世界一周旅行に出かけようとしていたのだ。
「しかも夢の半ばで殺されるなんて・・・それは化けて出たくもなるよな。そういえばお前と、ちょうど真逆なんじゃないか」
高橋にそう言われて、田中はハッとした。田中は1年間バックパッカーで世界中を周り、この春から新入社員として入社したばかりだった。
その夜、田中は再び夢を見たが、今回はそれまでと少し違った。夢の中でKさんと思われる男性と言葉を交わすことができたのだ。その人物は変わらず血まみれだったが、田中の言葉に頷き、微笑みながら消えていった。
朝になり、田中はあの電車に乗った。奇妙な出来事が起こる前に乗っていた、いつもの通勤電車だ。いつも空いていたあの席には、疲れ切った顔の60歳近い男性が座っていた。
一週間後、田中から高橋宛に絵葉書が一通届いた。
『高橋先輩、お元気ですか。僕は元気です。今この手紙はリオデジャネイロから書いています』
「田中、お前もか。やっぱりあの呪いは本物だったんだな」
絵葉書に描かれた、リオのカーニバルで陽気にサンバを踊る人達の写真を見ながら、高橋は深いため息をついた。
Kさんの呪いとして、語り継がれている話。Kさんが生前いつも座っていた席に座ったら最後、全員“職を失う”のだという。田中がいつもの通勤電車に乗ることは、二度となかった。
いかがでしたか。私たちが普段、何気なく過ごしている場所や状況は、思わぬ形で恐怖をもたらすことがあります。
今回紹介した短編の怪談話には、日常生活の中で起こりうる不思議な現象や恐怖が潜んでいます。
それではまた別の怪談話でお会いしましょう。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

オカルト研究家の洋子です。
私の最大の関心事は、日本の古くから伝わる怪談話や未解明の伝説です。
全国の隠れた怖い話や地域特有の伝説に魅了されており、それらを探求するために日本全国を旅しています。
それぞれの地域で語られる独特の怪談話は、その場所の歴史や文化を映し出しています。
オカルト研究家として、同じ興味を持つ人たちとこれらの情報を共有し、議論を深めています。
|
|
|