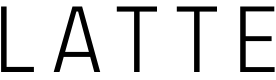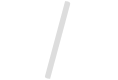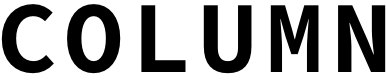「薬用養命酒」の生薬成分(14種類)と効能を解説。冷え性や滋養強壮におすすめ
養命酒に含まれている14種類の生薬成分を、東洋医学的に解説! 体を温め、冷え性や加齢による滋養強壮に効果的です。
こんにちは、薬剤師の田伏将樹です。
養命酒は、自然の生薬が原料の薬です。
お酒に生薬を漬けて成分を抽出させる「薬酒」という剤形のものです。

- 疲れやすくなった
- 元気が出なくなった
- 胃腸が弱くなった
- 冷えやすくなった
- 足腰がだるくなった
このように、何となく以前よりも衰えを感じるようになってきたな、というときに試してみたい薬です。
衰えを補ってくれる、14種類の生薬が組み合わされています。
各生薬は幅広い効能をもっていますが、代表的なものを、東洋医学の概念とともにご説明していきます。
東洋医学では、人体を構成する成分を「気・血・水」の3つに分類します。
この気・血・水が、十分に満たされており、かつスムーズに巡っていることが、健康な状態と考えます。
また、東洋医学には、成長または老化にかかわる臓器として「腎」(じん)というものがあります。
もって生まれた生命力を蓄えているのが「腎」です。
加齢による身体の衰えは、「腎」の衰えととらえます。
具体的には腰痛、足腰のだるさ、しびれ、関節痛、尿トラブル、冷え、不妊などです。
「イカリソウ」とも言われる草です。
昔から滋養強壮、強精の効果があると言われており、イカリソウ流エキスとしても、栄養ドリンクに含有されていることがあります。
杜仲の葉は、健康茶として知られていますが、生薬として使うのは樹皮です。
淫羊藿ともに、筋骨を丈夫にする生薬です。
腰や関節がだるく、冷えて痛むときなど、「腎」を補うのに適した生薬で、便通改善の作用もあります。
「腎」の強さは先天的(遺伝的)なものが大きいのですが、「脾」(胃腸)の働きが、それをバックアップしています。
体質的に「腎」が弱くても、生まれた後に、食べ物や大気からのエネルギーをしっかりと利用することができれば、「腎」が弱まるのを抑えることができるのです。
腎を補うための「気」の一部は、食べ物を消化吸収することで得られます。
身体を温める生薬です。
養命酒がシナモンの香りがするのは、この桂皮が入っているためです。
芳香健胃薬としての効果があります。
これも特有の香りがあり、ハーブでは「クローブ」と呼ばれます。
胃腸を温めることで、消化器の働きを整えます。
薬用ニンジンは、漢方薬に欠かせない生薬です。
消化器、呼吸器ともに働きを良くさせて「気」を増やします。
「気」は生命活動のエネルギーとも言える根本のものです。
もし「気」が足りなければ、血と水も十分に作り出せなくなっている可能性があります。
なお、胃腸が冷えると消化吸収のはたらきが悪くなり、気の生産力が低下します。
普段の食生活においても、冷たいものの飲食に気をつけてください。
血を補う、潤す作用のある生薬です。
足腰の衰えに使う漢方薬に、よく配合されています。
血を補うとともに、痛みを和らげる作用もあります。
「気」が十分に体を巡っていることが、健康・若々しさに欠かせません。
血や水も「気」によって運ばれますので「気」が巡っていなければ、血と水の流れも滞ってきてしまいます。
血の流れが悪いと、しびれ、こり、痛み、冷え、肌荒れを招きます。
ベニバナです。
漢方薬では瘀血の治療(血行を改善するため)に広く使われています。
※ただし、妊婦さんは控えるべき生薬です。
名前には、「婦人にとって役に立つ薬」という意味があります。
血の巡りが悪くて、月経不順や月経痛が起こるときに使われる生薬です。
ショウガ科。
色付けのスパイスでは、ターメリックと言われます。
生薬としては、血行を良くするはたらきがあります。
「水」の代謝を改善し、関節の痛みやしびれをとる生薬です。
香りが良く、体を温めるとともに気持ちを落ち着かせます。
マムシを精製したものです。
マムシは、滋養強壮に昔から利用されています。
栄養ドリンクには「ハンピチンキ」として入っています。
そして15個目の成分として、アルコールが入っています。
少量のアルコールは、血流を良くし、消化を促進しますので、生薬の吸収と、全身への薬の巡りを助けます。
ちまにみ、アルコール分は14%。
日本酒やワインと同程度、含まれています。

養命酒はアルコールとともに、体を温める生薬がたくさん使われています。
冷え性の人には適しますが、ほてりや、のぼせの出やすい人は気をつけてください。
また、女性で月経過多のときも、慎重に使った方がいいと思います。
「腎」を補うことが、老化の防止につながります。
逆に胃に負担をかけたり、過労・寝不足・性生活の乱れで、「気」(エネルギー)を浪費していると、「腎」の衰えを加速し、老化を早めます。
東洋医学で日頃の「養生」を何より大事とするのはこのためです。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|