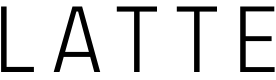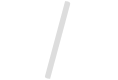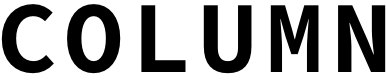漢方薬剤師おすすめ!花粉症のつらい症状を和らげる漢方薬9つ
花粉症に効く漢方薬を生薬認定薬剤師が解説!鼻水やむくみ、目ヤニ、痒み…つらい症状を緩和させたいときにおすすめの漢方薬9つとは?
こんにちは、薬剤師の田伏将樹です。
花粉症の人にとってはつらいシーズンがやってきました。
今回は、お勧めの漢方薬をご紹介します。
「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」というアレルギー性鼻炎のときの漢方薬もよく知られていますが、花粉症に使えるのはこれだけではありません。

体には自然からの影響を防ぐ力を持っています。
外からの悪影響から、体を守っているのは「衛気(えき)」という「気」の一つです。
体の表面をくまなく覆って体表面を保護しています。
この「衛気」が強いかは、皮膚や粘膜の細胞の構造・働きがしっかりしているかどうかが重要です。
しっかりしていれば、花粉の侵入を防げますし、水液の過剰な分泌も起こらないというわけです。
よって、花粉症の治療には水液代謝の改善と、「衛気」の補助が必要となります。
主に、症状を和らげるためには水液代謝を良くする漢方薬、体質改善のためには「衛気」を補助する漢方薬を選びます。
花粉症の漢方薬として有名な「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」は、このタイプの花粉症に適します。
体を温めながら水液代謝を改善する漢方薬で、体が冷えたときに症状が悪化する場合に効きます。
特に、冷えが強くて寒がりな人、普段から体が弱く、風邪のときよく寝込んでしまうような人には、「麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)」が使われます。
発症期の漢方薬でも長期間使用することがあるかもしれません。
血圧が高い方、心臓に疾患のある方など長期連用は避けるべき漢方薬もあります。
不安な方は専門家にご相談ください。
「小青竜湯」で動悸や胃もたれなど不具合を起こす方には、「苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)」を代わりに使います。
顔や目のまわりに浮腫(むくみ)が現れる症状には、「越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)」があります。
消炎作用と、アレルギー反応で起こる浮腫を引かせる作用のある漢方薬です。
炎症が強くて熱感を伴うと、鼻水などの水液は徐々に濃く黄色く粘っこくなってきます。
このときは「辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)」を使います。
「辛夷」(シンイ)は鼻の通りをよくしてあげる生薬です。
「小青竜湯」は温めて治すのに対して「辛夷清肺湯」は炎症を冷まして治します。
のどが乾燥し、いがらっぽくて咳が出るときには「麦門冬湯」(ばくもんどうとう)が使われます。咳止めと、のどを潤す効果があります。
普段からよく風邪をひく、汗が出やすいという人は「衛気」の力が弱いと考えられます。
「衛気」を補助する代表的な薬として「玉屏風散(ぎょくへいふうさん)」があります。
「衛気」のエネルギーは食べたものから作られますので、食欲がない、生ものなどですぐ下痢をする人は、「衛気」が弱まりやすいです。
また、水液代謝にも胃腸は大事です。
胃腸機能から整えていきたいときは、「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」が用いられます。
消化吸収の力がアップすれば、「衛気」が満たされ、体が守られます。
色白で汗が多くて、足や関節に水がたまりやすい、水ぶとり体質の人は、疲れやすく抵抗力も弱い人です。
この体質改善に使われるのが「防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)」です。
これら「玉屏風散」「補中益気湯」「防已黄耆湯」に共通して含まれるのが「黄耆(オウギ)」という生薬です。
黄耆は「衛気」を補助するための重要な生薬と言われています。
普段から「黄耆」のお茶を飲んでおくだけでも違いが現れるかもしれません。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|