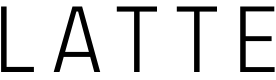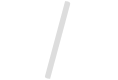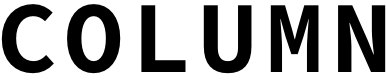「妊娠?じゃあ仕事辞めて」ってアリ?働く女性の出産環境を守る「男女雇用機会均等法」とは
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
働く妊産婦への配慮として、法律ではどのような定めがされているかを解説するシリーズの2回目です。
前回のコラム「妊娠・育児中も仕事は続けたい!働くママが知っておくべき労働基準法6選」に続き、今回は男女雇用機会均等法編をお送りします。

職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律です。
女性の母性健康管理の措置についても定められています。
- 男女雇用機会均等法における、母性健康管理の定め
(1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(第12条)
事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
- 妊娠23週までは、4週間に1回
- 妊娠24週から35週までは、2週間に1回
- 妊娠36週以後出産までは、1週間に1回
- 医師等の指示に従って必要な時間
妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。
- 妊娠中の通勤緩和(時差通勤、勤務時間の短縮等の措置)
- 妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、休憩回数の増加等の措置)
- 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、休業等の措置)
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、医師等から女性労働者に出された指導事項を的確に事業主に伝えるためのカードです。
女性労働者からこの「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出された場合、事業主は記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
「妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱い」と考えられる例
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをすることはできません。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、その回数を引き下げること
- 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような、労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をしたり、賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

(4)紛争の解決(第15条~第27条)
母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。
妊娠中・出産後の女性労働者に対して、事業主は配慮をする必要があり、不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
罰則規定はありませんが、「妊娠したから辞めてほしい」などと女性労働者に強要することは法律違反となります。
事業主には、慎重な対応が求められます。
次回は育児介護休業法編をお送りします。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|
|