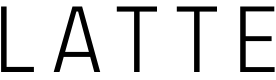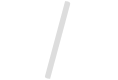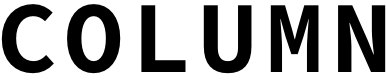身近な介護制度の利用例!ケアプラン作成時の流れと注意点
こんにちは。ベストウェイケアアカデミーの馬淵と申します。
さて、前回はアセスメントについて見ていきました。
アセスメントの重要性、分かって頂けたでしょうか?
今回は、アセスメントが終了し、いよいよ具体的にケアプランを作成していくことになります。

「ケアプラン作成」といいましたが、いきなりこれがサービスに結びつく、というわけではありません。
まずは「原案」を作成することから進めていきます。
アセスメントを行うと、ある程度どのようなサービスを使っていけばいいのか、どれくらいの頻度で使っていくのか、などは分かってきます。
しかし、そこでいきなり「Go」を出すのは実は早すぎるのです。
「いや、早くサービス使いたいので、お願いします!」とお願いされても、肝心なことが抜けています。
まず、「どこの事業者から来てもらうか?」です。
事業者を決めなければなりません。
訪問介護を使うと決まっても、どこの事業者を使いたいのか、空きがあるのか、などをあらかじめ考えなければなりません。
もちろん、「利用者本位(利用者さんが主役)」なので、自由に決めることができます。
また、どこの事業者にお願いすればいいのか全く分からない利用者さんでも、ケアマネジャーさんが一覧表を持っていますので、そこから選ぶというのも方法ですし、インターネットや口コミで選ぶのもOKです。
そして、もう一つ肝心なのが「いくらかかるのか」です。
介護保険は「保険制度」ですから、病院に行ったとき同様、一部負担金が生じます。
介護保険の場合は原則1割負担(平成27年4月より一部2割負担)となっていますので、これもあらかじめ月にいくらくらいかかるものなのかを原案によって知ることが可能です。
このように、サービスを利用する前に知っておかなければならないことをこの「原案」で知ることができるのです。
そして、原案が出来上がると、それらを元に「サービス担当者会議」が開催されます。
担当のケアマネジャーさんが、事業者を集めて顔合わせと今後サービスをどのような視点で提供していくかを話し合う会議です。
「サービス担当者会議」といっても、利用者さんや家族さんも参加することになります。
「サービス担当者会議」は、利用者さん家族さんが参加することに大きな意義があります。
利用者の立場として、家族の立場としてどうすればいいのかわからない、というお声も多いので、次回はこの「サービス担当者会議」について詳しく見ていきたいと思います。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

はじめまして。
大阪府豊中市でかいごの学校をしております、ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士と申します。
主として介護系受験対策講座の講師などで呼ばれたところへ飛んでおります。
また、教育分野をより深く探求するため、現在奈良教育大学大学院教育学研究科へ所属しております。
所属学会:日本児童青年精神医学会
|
|
|