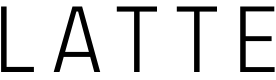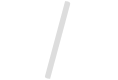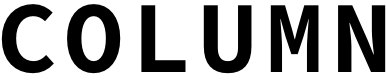大相撲、地位による待遇の格差とは。力士の階級制度 -序ノ口~横綱-
相撲は、勝ち進んでいくほどに、番付が上がっていきます。
下は序ノ口から、上は横綱まで、10の階級にランク分けされています。
今回は、それぞれの名前と特徴をご紹介したいと思います。
大相撲で最下位の地位です。
番付に記載される文字があまりに小さいので、序ノ口は俗に「虫メガネ」と呼ばれています。

序ノ口のひとつ上の階級です。
大相撲には、地位による待遇の格差が存在し、番付により身に着けられるものに違いがあります。
序ノ口と序二段は、年中浴衣で、真冬でも一重の着物だけの姿です。
マフラーやコートを身にまとうことは、許されていません。
厳しい世界ですね。
序二段のひとつ上の階級で、幕内、十両、幕下に次ぐ地位です。
番付表の上から三段目に名前が記載されることに由来しています。
序ノ口・序二段の履物は、下駄と決まっていますが、三段目からは雪駄を履くことが許されます。
しかし、三段目までは、まだ足袋を履くことはできず、裸足です。
三段目の上で十両の下の階級です。
序ノ口から幕下までは、取的(力士養成員)で、まだ関取ではありません。
幕下と十両、ここには、他のどの地位よりも大きな差があります。
関取として、一人前に扱われるのは十両からです。

序ノ口・序二段・三段目・幕下までは、生活費は部屋で面倒見て貰えるものの、養成員という立場から給料は支給されません。
幕下までは、プライベートでも結婚できないなど、厳しい掟があります。
ハングリー精神を養うという側面からも、十両に上がるまでには徹底的に差が設けられ、その待遇は「天国と地獄」ほど違うと言われます。
十両は、幕内(平幕)の下・幕下の上に当たります。
これより上の力士は、晴れて関取として扱われます。
- 力士の証である大銀杏を結うことを許され、幕下以下の付人がつき、月給・褒賞金も支給されます。
- 化粧まわしをつけての土俵入り、塩まき、力水の儀式も十両から行ないます。
- 幕下までは大部屋ですが、十両からは個室を与えられます。
- 羽織袴が着られるようになり、白足袋も履けます。
- 移動にも、これまでは電車やバスなど公共交通機関しか利用できませんでしたが、タクシーも利用できるようになります。
前頭以上を「幕内」と言います。
その幕内力士の中で、横綱と三役(大関・関脇・小結)以外の力士を、「前頭」と呼びます。
役のついていない力士ということで、平幕とも呼ばれます。
大関・関脇・小結を三役と言い、小結は三役の中では一番下の地位です。
横綱大関陣との対戦が組まれ、実力を問われる地位でもあります。
小結よりひとつ上の地位です。
大関、そして横綱も見えてくる地位です。
関脇が大関に昇進する場合には、2、3場所続けて優秀な成績を挙げる必要があり、連続して平均11勝以上の成績が、大関昇進への条件と言われています。
また、関脇は原則として1回の負け越しで、小結以下に陥落します。
横綱に次ぐ地位で、三役の中の最高位です。
二場所連続して負け越さない限り、下位に落ちないのが最大の特権です。
前の場所で負け越し、次の場所で勝ち越さないと、その地位から陥落する絶体絶命の大関を「角番(かどばん)大関」と呼んでいます。

相撲界の頂点で、最高位の称号です。
神事を発祥とする相撲の象徴として神をも宿る存在とし、ただ強いだけでなく、横綱としての品格も問われます。
負けても降格することはありませんが、その責任は限りなく重いものです。
以上、大相撲の階級についてでした。
相撲観戦のご参考になれば、幸いです。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

|
|
|