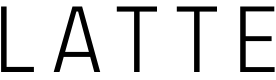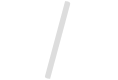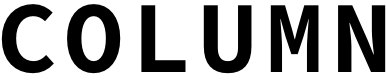「UMAMI(うまみ)」とは何か?昆布にまつわる日本の歴史と文化 -地域別に見たさまざまな調理法-
こんにちは、昆布料理研究家の岩佐優です。
私達の舌で感じることの出来る、味の基本は五つ。
「塩味」「酸味」「苦味」「甘味」、そして「うま味」です。
中でも「うま味」は約100年前、日本人によって発見されました。
日本の昆布は、北海道や東北など北の海でしか採れません。
古来、北海道で船に積み込まれた昆布は「昆布ロード」と呼ばれる海路を経て、全国に運ばれました。
うま味は、かつお、昆布(こんぶ)などに多く含まれる、グルタミン酸、イノシン酸などによって作り出されます。
お母さんの母乳にも成分が入っているといいますね。
今では世界でも広く認められ「UMAMI(ウマミ)」は世界共通語です。
そして昆布は、古くから「比呂米(ひろめ)」「広布(ひろめ)」「夷布(えびすめ)」と呼ばれ、縁起の良いものでした。
今でもお披露目式や婚儀には「名を広める」「恵比寿女(=えびすめ、縁起良い女性)」という意味で、欠かせないものです。
その昔、武士の社会でも、熨斗鮑(のしあわび)と搗栗(かちぐり)と昆布を合わせ、"敵を討って(鮑)、勝って(搗)、喜ぶ(昆布)"と語呂を合わせて、贈り物とされたのですね。
かつての風習として、日本の食卓には、沢山の海藻料理が並んでいます。
四方を海に囲まれた日本は、海産物を食してきたのは自然なことですが、魚介類を食してきただけでなく、海藻を食べる文化は独特なものなのです。
その歴史は大変古く、縄文時代から海藻を食べていたことが分かっています。
日本人ほど海藻を食べる民族は、世界でも珍しいと言われていますよ。

さてその昆布ですが、スーパー、デパートにはたくさんの種類の昆布が並んでいますね。
どれを選び、何を買ったら良いのか迷いませんか?
その前に、日本の皆様がどのように昆布を食しているのか、お教えいたしましょう。
まず、地域によって食べ方が違います。
昆布の食べ方や量は、地域によって異なり、昆布の歴史的背景と関連があるようです。
- 北海道
主に出しとして利用しています。
- 三陸地方
細く刻み、薄い紙状にしたすき昆布を食べます。
- 北陸地方
出しはもとより、肉厚の真昆布を、おぼろやとろろとして、けずり昆布にして食べます。
- 関西・中京
出しに利用するほか、おぼろ・とろろ昆布、特に佃煮にして食べます。
- 関東地方
主に出しに利用し、加工品も食べますが、食べる量は少ないようです。
- 九州・沖縄
釧路・根室産の長こんぶを肉や野菜と炒めたり、煮込んだりして食べます。
本当にざっくりですが、このようなところでしょうか。
それぞれの食べ方にどの昆布を使ったら良いかは、前回のコラムをご確認頂ければと思います。

「美味しく食べたい。美味しく食べさせたい」
そんな思いを、私たち日本人は持ち合わせています。
そして毎日の食事を美味しく健康に、自然の恵みに感謝していただきます。
「昆布料理」は、そんな気持ちと食文化が生んだ、優しい調味料でもあるのでしょう。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア
|
|
|