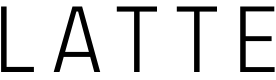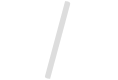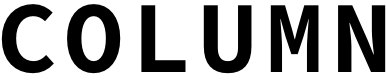インコや文鳥をペットに!鳥を飼うときの注意点まとめ
インコや文鳥など、鳥をペットとして飼う人が増加中!鳥の体のしくみや、病気のサインなど、鳥を飼う場合の注意点を解説します。
ペットの小鳥は、ペアで鑑賞するよりも、手乗り鳥として楽しむ方が増えてきました。
鳥の体のしくみについて学びながら、気をつけたいことを解説していきたいと思います。

鳥の口は、歯のないくちばしとなっています。
種類により、真っ直ぐなものや、下向きに曲がったものなどがあります。
これは、食べ物を探し出して取り、食べるのに適した形になっています。
くちびるのようには柔らかくないので、水を飲む場合は口に入れてから上を向いてのどに流しこむように飲む鳥が多いです。
鳥の食べ物は主に、穀類、種子類、フルーツや、葉っぱ、虫などです。
鳥の目は、飛びながら物を見るために視力に優れ、すぐに対象物にピントを合わせることができるようになっています。
飼育している小鳥たちなどは、片方の目で物を見ます。
肉食の鳥たちはだいたい目が二つ正面を向いており、獲物までの距離が正確に測れるような作りとなっています。

じっと見つめられるのが苦手な鳥も
人からじっと見つめられるのは、鳥にしてみれば敵に狙われているように感じ、実は怖い思いをさせてしまっているかもしれません。
ただ、手乗りで育てられたり、長い間飼育されてきた小鳥などは、人を見慣れているせいか、それほど嫌がりません。
鳥は自分の体をくちばしでかいたり、羽をくわえてしごき、手入れを怠りません。
ですが、顔周りだけは届きません。
そこで、お互いにつつきあったり、かいたりしています。
頬や頭を上手く足先で、掻く様子もよく見かけます。
くちばしを止まり木にこすりつけるしぐさは、汚れを取っているのです。
手乗り鳥も、人が指で目やくちばしのわきなどをかいてやると喜びます。
また、鳥の方から首を曲げて寄ってきて、顔をかいてほしいと、要求してくることもあります。
飼育しているセキセイインコなどが、頻繁に顔やくちばしを何かにこすりつけてばかりいる場合は、カイセンダニ等が寄生していることもありますので、注意して観察してください。
疑わしい時は、獣医さんに診てもらいましょう。
鳥の体はほとんどが羽に覆われています。
羽は飛ぶために進化して、とても軽く、空気を含んで保温性も抜群です。
人は水鳥の小さな羽毛、ダウンを集めて、布団や服などに利用していますね。
羽の生え変わりは、年1~2回
羽は、毎年1~2回生え変わっています。
なお、翼の大きな羽「風切羽」が抜けてしまうと、飛べなくなります。
水鳥類は繁殖で、陸上でヒナを育てる時期に合わせて、換羽(とやとも呼ぶ)を一気に済ませてしまいます。
他の鳥は少しずつ抜けては生え変わり、まるきり飛べなくなる事態にはならないようになっています。
オスの鳥たちは繁殖期に美しい婚姻色の羽に生え変わり、メスの気をひくものが多くいます。
特別な形の羽が生えてくる種類もおり、オスはさえずったり羽を立ててダンスをしたり、メスに気に入られようとして一生懸命です。
きらびやかな目玉模様がある扇型の尾羽を持つ、クジャクが良い例でしょう。
伸びる途中の羽を筆毛といい、初めはとがった羽軸の先から花びらのように羽がどんどん伸びていき、1枚の羽になっていきます。
なお、羽軸には血が通っています。
折れてしまうと、羽軸はストロー状態のため、出血してしまい止まりにくいものです。
こんな時は折れた羽のみを抜いてしまいましょう。
また、すぐに新しい羽が生えてきます。
小さな羽の場合は自然に血が止まり、成長せずに抜けていきます。
完全に羽が伸びきると、もう血は通っておらず、羽の根元だけが生きているようです。
羽軸は中空になっています。
自然に抜け落ちるまでは、羽を抜くと少し痛いようです。
人の髪の毛と同じような感じなのでしょう。
だからでしょうか、伸びている途中の筆毛を触られることは大変嫌いますので、注意しましょう。
鳥たちは腰の辺りから分泌している脂をくちばしで取っては、羽に塗りつけていきます。
水に接することの多い鳥ほど脂分が多いようです。
健康な鳥の翼は、少々の雨ははじいてしまいます。
鳥にとって大変重要な羽は、毎日ていねいに手入れをし、水浴びなども欠かさないものです。
ですから飼育している鳥も羽つくろいや、水浴びをしない、というのは、体調が悪い証拠となります。
昼間に丸くなって、羽のつやもなく、元気がない様子であれば、一度診察してもらうことをお勧めします。
鳥の特徴的な器官として、食道の前に「そのう」という袋を持っています。
食べたものを一度ここに貯めておき、水分でふやかして柔らかくしています。
手乗りのひなを育てたことがあれば、見たことのある方もいるでしょう。
綿毛のひなのうちですと、よく見えるところですから、挿し餌のフードを与える量の目安がわかります。
なお、そのうでは、消化は行われません。
ですから、食べたものが胃へと進まず、だんだんと硬くなってきたら、「食滞」という症状で、ひなにはとても危険です。
早い時期なら、ぬるま湯を少し飲ませて、そのうを軽くもんでやり、保温に努めると治る場合もあります。
ですが、体温低下や栄養不良、細菌類の感染などによる場合には、素人療法では回復しませんから、獣医さんにお願いしましょう。
鳥のひなは小さくて、免疫力・体力も乏しいため、早期発見・早期治療が大切です。
鳥のふんについて
鳥は飛ぶために食べたものを素早く消化吸収して、すぐにふんとして出してしまいます。
哺乳類と違って、ぼうこうはありません。
おしっこは、ゼリー状の尿酸として出しています。
鳥のふんを観察してみてください。
黒っぽい部分に付いている白や黄色っぽいものが鳥のおしっこなのです。
環境が変わったり、新しい人や鳥、他の生き物が近くに来たりしますと、ストレスを感じて、水っぽいふんをすることがあります。
これは特に心配いりません。夏場などで水の飲み過ぎでも起こります。
ふんの塊がなく全体に柔らか過ぎるふん、黒っぽくて粘り気があるふん、いつもと違う色やにおいがする場合などは、他に症状がないかどうか、様子を見てみましょう。
ふんの状態で判る病気も多くあります。
ひなの時と一人餌に切り替わった後では、ふんの状態は変わります。
鳥の足には、羽はなく(品種改良により生えていることもある)細かなうろこ状の硬い皮膚で覆われています。
研究により、鳥は恐竜の子孫にあたるそうなので、足が一番恐竜に似た部分でもありますね。
一番大きな鳥であるダチョウのくちばしに、もしも歯が生えていたら、もっと早く恐竜の子孫ではないかと研究がすすんでいたのではないでしょうか?
ペットの鳥たちの足の指は前が3本、後ろに1本付いていることが多いです。
足を交互に動かして歩いています。
チョンチョンと両足を揃えて飛び跳ねるように移動します。
インコやオウム類
足の指は前に2本、後ろに2本付いています。
このおかげで木に上手く登ることができます。
片足でえさをつかんだまま、食べることもできます。
飼っている鳥におもちゃや止まり木を用意する場合は、鳥の性質に合わせたものにしましょう。
大きな積み木のようなものをぶら下げても、文鳥は上手く遊べませんし、天井に粟の穂を付けますと、インコは食べに行けますが、文鳥にはとてもむずかしいことでしょう。
変な姿勢で寝ているように見えても、その恰好が楽らしい
鳥が止まり木で眠る時に、片足をあげて腹の羽にしまい、首を曲げて片方の翼に頭をしまい込んでいることがあります。
人からするとびっくりしてしまう姿勢ですが、鳥たちはかえってバランスが取れて休めているようです。
巣の中で眠る場合は、足はそのままで、頭だけしまっているようです。
鳥を捕まえたり、遊んだりする場合の注意点
鳥の首や足は細いですし、胸全体で呼吸をしているようなところがあります。
鳥を捕まえる際は強く握りしめないようにしてください。
逃がさないように上手くつかむにはコツが要りますし、上手な人に指導してもらうのが良いと思います。
初心者や子供が鳥をつかむと、足や羽を痛めたり、きつくにぎってしまって、呼吸ができずに息絶えてしまうこともあるのです。
鳥の体温は高く、40度くらいあります。
ですから手乗り鳥と遊ぶばあい、真冬に冷たい手で遊ぶのはあまり感心しません。
なるべく手を温めてから、遊んであげるようにしましょう。
鳥が病気になった時には、保温が何より大切です。
今は色々な保温器具が市販されていますから、一つは用意しておきたいものです。
体温が保たれていれば、食べたものもきちんと消化されて、早く回復していくことが期待できます。
鳥の体のしくみについて、学び、飼育している鳥とのより良い生活ができるといいですね。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

犬のブリーダーをしています。動物に囲まれて生活していて毎日、多忙ですが、
色々な発見があり楽しいです。ペットに関してのご相談お受けいたします。
|
|
|