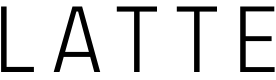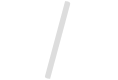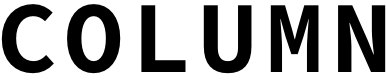もっちり可愛い!文鳥の種類や飼い方、必要なもの、健康管理のコツ
可愛らしい「文鳥」は、ペットとして大人気!いろいろな種類や飼育のために必要な道具・飼い方のポイント・健康管理の重要性などを解説。文鳥初心者の飼い主さんは、家に迎える前にぜひご一読ください。
気が強くてちょっとしたことで、「るるる―」と声を出して怒る文鳥。
しぐさが可愛らしく、見ていて飽きません。
オスのさえずりとダンスもリズミカルです。
こちらまで、気分が明るくなりますね。
今回は、ペットとして大人気の文鳥について、種類や飼い方・健康管理の重要性などを解説します。
原産地は、インドネシアのバリ、ジャワ島です。
英語では、「Java Sparrow(ジャワスパロウ)」と呼ばれ、ジャワのスズメという意味です。
世界中で飼育されており、様々な品種が生み出されてきましたが、原産地では、稲を食べる害鳥とされて、数を減らしています。
日本では、江戸時代初期に輸入されて、後に繁殖が盛んになり、飼い鳥としての飼育が始まりました。
真っ白い白文鳥は、日本で作出された品種です。
大きさは 頭から尾の先まで約14cm。
体重は、約25gです。
平均寿命は、7~8年です。
長生きの鳥は、15年くらい生きた記録があるそうです。
原種は、頭、腰、尾羽が黒。
頬が白く、お腹は薄いあずき色をしており、胸と背中はグレーになっています。
くちばしと目の周りのリングが赤く、日本人好みの和風な雰囲気の色合を持っています。
ノーマル文鳥、または並文鳥と呼ばれています。

まずノーマル文鳥の胸に白い羽が混じるものが作られました。
舞い散る桜の花びらに見立てて、桜文鳥と名付けられました。
これも日本人ならではのイメージで、粋な名前の付け方だと思います。
桜文鳥の白い羽は背中や頭、風切羽にまで現れます。
白い度合の多いものは パイド文鳥と呼び分けられています。
体の半分以上が白い感じでしょうか。

そして以前は一番人気だった白文鳥。
「はくぶんちょう」とも読みます。
明治時代に愛知県の弥富市にて、突然変異で真っ白い文鳥が生まれました。
弥富市は文鳥の飼育が盛んで、白文鳥が増やされて現在に至っています。
これはアルビノとは違い、目は黒く、真っ赤なくちばしと体の白さが美しい品種です。

これは1970年代にヨーロッパで、固定された品種です。
黒い羽が茶色に変化しています。色の薄いものと濃いものがいます。
茶系のグラデーションと赤いくちばしや目のリングがよく似合っているおしゃれな文鳥です。
先のシナモンにさらに淡色化の遺伝子が合わさり、全体に白っぽいイメージ。
優しいクリーム色の文鳥です。
目は赤くなっています。

比較的新しい品種で、ノーマル文鳥の色合がパステル調に薄くなっているものです。
濃いものは「ダークシルバー文鳥」、薄いものは「ライトシルバー文鳥」と呼ばれています。
小鳥には、少ない色変わりで、人気の高い品種です。
この他にも、次のような品種の文鳥がいます。
大変珍しい「ブルー文鳥」というわずかに青味がかっている文鳥や、ノーマル文鳥で頭と尾羽が茶色がかっている「アゲイト文鳥」。
色合いが明るく変化した赤目の「クリームイノ文鳥」や、「シルバーイノ文鳥」など。

文鳥は、インコに比べればカラフルではありませんが、このくらい色変わりがいれば、きっとお気に入りの文鳥が見つかることでしょう。
文鳥は大き目のフィンチですし、夜はつぼ巣に入って眠りますので、大き目の鳥カゴを用意してあげましょう。
止まり木は、上下に2本取り付けます。
足を揃えてぴょんぴょん飛ぶ歩き方をしますから、止まり木も2本の間をはねて行ったり来たりすると良い運動になります。
つぼ巣は、鳥の大きさや羽数に合ったものを付けます。
水入れは小さめでも構いませんが、文鳥は水浴びが大好きです。
体が入れば水浴びをしてしまいます。
仲の良いペア、一緒に育ったきょうだい以外では喧嘩をしますので、基本的には1羽飼いをお勧めします。
エサは、市販の混合餌、青菜、ボレー粉など。
未熟な青米も好むようです。
先にお話したように、文鳥は水浴びが大好きです。
毎日水浴び用の入れ物で、水浴びをさせてやりましょう。
冬に寒いからと、お湯をいれないようにしてください。
冷たい水のままでないと、大事な脂分が流れて羽を傷めてしまいます。
文鳥のなめらかな美しい羽は、日ごろの羽繕いによって生み出されます。
文鳥のふんは、少し水分が多いので、こまめに掃除する必要があります。
梅雨から、夏場は、つぼ巣や止まり木にダニがわくことがあります。
時々洗って熱湯消毒をして、日光で完全に乾かします。
交代で使用しますと長持ちします。
つぼ巣には、糸が使われているものもあり、糸がほつれていないか点検しましょう。
文鳥の足や爪に引っかかり、怪我をする場合もあります。
文鳥を飼育している方は、毎日健康チェックを忘れずにしましょう。
若いうちは、特に病気にかかりやすいので、注意してください。
- 呼吸がおかしい
- 昼間、羽を膨らませて寝ている
- 口をよく開ける動作をする
- 水浴びをしない
- 普段と違うふんをしている など
小鳥は病気を隠そうとしますので、人が気が付いた頃には、病気が進んでしまっている場合もあります。
また、小さくて体力がないため、すぐに弱ってしまいます。
ですから、気が付いたらすぐに病院へ行くくらいで、丁度良いのです。
文鳥は、いつも活気があり、普段のなき声もあまりうるさくありません。
文鳥との暮らしはきっと楽しいものとなることでしょう。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

犬のブリーダーをしています。動物に囲まれて生活していて毎日、多忙ですが、
色々な発見があり楽しいです。ペットに関してのご相談お受けいたします。
|
|
|