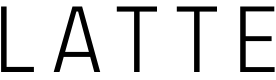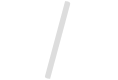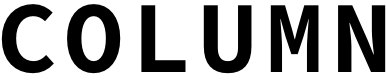ビタミンDの効能!ビタミンDを多く含む食べ物と、効果的な過ごし方 (1/2)
ビタミンDの効果・効能、多く含まれる食材とその含有量を紹介。骨を強くするので、閉経後の女性や高齢者の骨粗しょう症予防にも。妊娠に必要な栄養素としても注目されています。
こんにちは、薬剤師の宮本知明です。
今回は、ビタミンDの効能と多く含まれる食べ物、上手に摂取する方法について解説します。

ビタミンDは、骨の主要成分であるカルシウムの吸収促進と、骨の再構築に必要な栄養素です。
不足すると、乳児・幼児・小児などの成長期の「くる病」と、大人では「骨軟化症」を引き起こす可能性があります。
どちらも、共に骨が柔らかくなって、背骨や肩から手首までの腕の骨、腰から足首までの骨が曲がったり変形したりする病気です。
他にも、閉経後の女性や高齢者で、ビタミンD不足が長期間に渡ると、骨粗鬆症のリスクが高くなります。
ビタミンDは、妊娠する力を高める栄養素としても注目されています。
妊娠中にビタミンDが不足すると、「妊娠糖尿病」や「妊娠高血圧症候群」などの妊娠合併症にかかりやすくなります。
赤ちゃんが成長するにつれて、カルシウムが必要になっていきます。
カルシウムの調節に関わっているビタミンDが少ないと、小さな赤ちゃんが生まれやすくなったりすることがあります。
しらす干し約6g(大さじ1杯分)食べれば、1日の目安量を摂取することが可能です。
しらすかけご飯だけでなく、トーストとしらすを一緒に焼いて食べるのも美味しいですよ。
いくらも、ビタミンDを多く含む食品です。
約17g(大さじ1杯分)で、1日の目安量を摂取できます。
お寿司や海鮮丼を食べるときに、意識していくらを選んでみましょう。
いつでも食べやすい食材で、1切れ食べれば十分にビタミンDを摂取することができます。おにぎりの具を鮭おにぎりにしたり、お弁当に一切れ入れて、ビタミンD摂取するのもいでしょう。
きくらげは、中華料理によく使われる食材です。
乾物として売られているため、保存もしやすいのも魅力です。
中華丼や卵スープに入れるなどして摂取してみましょう。
ビタミンDには、動物起源の「ビタミンD3」と植物起源の「ビタミンD2」があります。
ビタミンD3は、コレステロールが体の中で作られる際の代謝産物である「7-デヒドロコレステロール」と、紫外線による光化学反応で作られます。
この反応は、主に動物の皮膚表面で進行すると考えられています。
ビタミンD2は、植物ステロールである「エルゴステロール」が植物の中で紫外線と光化学反応を起こして作られます。
7-デヒドロコレステロールは、別名「プロビタミンD3」と呼ばれています。
ビタミンD3は、食べ物でなくても、人の体の中で作ることができます。
2種類のビタミンDは、体内で肝臓と腎臓で酵素反応を経て、活性型ビタミンDへと変化し、体に作用します。
前述の通り、ビタミンDは、人の体の中でも作ることができます。
皮膚表面にあるプロビタミンD3と呼ばれる物質が紫外線と反応してビタミンD3へと変わります。
緯度や季節によっても異なりますが、一般には、10分から20分足らずの日照量で必要量を満たすと言われています。
|
|
|
-
Facebook で CHECK♡
- Facebook でシェア
- Twitter でシェア

薬剤師/ジェモセラピスト/漢方ソムリエ。病院薬剤師を経て“薬と共存しない生活”の念いからホリスティックな健康観と出逢う。現在は、新婚女性、新米ママさんを西洋医学・東洋医学・自然療法の良さを合わせた統合医療の知識をもった“ホリスティックな健康観を持つ女性”に育成する活動をしている。
ブログ
http://ameblo.jp/blacknightz/entrylist.html
facebook
https://www.facebook.com/tomoaki.miyamoto.16
公式HP
http://tomoakimiyamoto.strikingly.com/
|
|
|